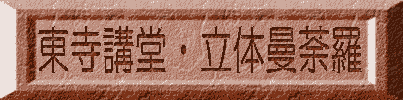
じこくてん
持国天立像
木造彩色 高さ:約1.8m
国宝(平安時代 839年)
元来は古代インド神話に於ける方位の守護神を起源としている四天王のうち、
東方の守護神。四天王は釈迦の説法に感銘し佛教に帰依、
釈迦入滅後の法の守護を託されたと言われています。
持国天の梵語名はドリタラーシュトラといい、提頭頼叱と音写されます。 「国土を支えるもの」との意味を持つことから「持国天」と呼ばれます。
宝髻(ほうけい)を結い、天冠台(てんかんだい)を被っています。 経説では、持国天像は片手で宝珠を持つとされるが、 この像は右手に三鈷戟(さんこげき)を執っています。 これは空海が意図的に行った改変であると言われています。 左手には剣、口は喝を入れているように開き忿怒の表情で邪鬼を踏みつけています。
平安時代、承和6年(839年)に完成。
持国天の梵語名はドリタラーシュトラといい、提頭頼叱と音写されます。 「国土を支えるもの」との意味を持つことから「持国天」と呼ばれます。
宝髻(ほうけい)を結い、天冠台(てんかんだい)を被っています。 経説では、持国天像は片手で宝珠を持つとされるが、 この像は右手に三鈷戟(さんこげき)を執っています。 これは空海が意図的に行った改変であると言われています。 左手には剣、口は喝を入れているように開き忿怒の表情で邪鬼を踏みつけています。
平安時代、承和6年(839年)に完成。
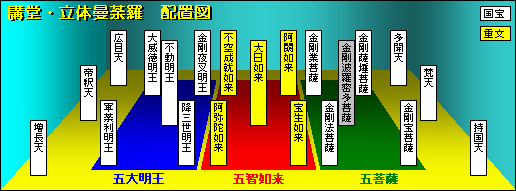
|
 |