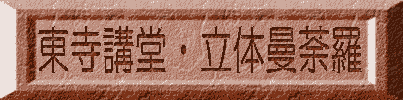
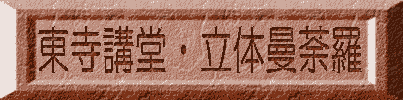
左のメニューを非表示にする。
このコーナーは左メニューありで1000ドット程度、
メニューなしで約700ドット程度の幅で作成されています。
| 講堂は天長二年(825)に空海(弘法大師)の発願で着工し、空海が高野山で入定(死亡)の年、 承和二年(835)に完成しました、空海は残念ながら、完成した講堂を見る事はなかったのです。 文明十八年(1486)の土一揆の争いで焼失し、 現在の講堂は延徳三年(1491)、創建時の基壇の上に再建されました。 |
|||||||||||||
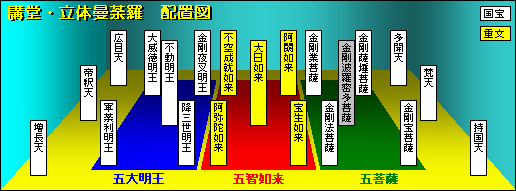
|
 |
||||||||||||
| 東寺講堂には普通は絵画として表現される「曼荼羅(まんだら)」を、 より体感できるよう「立体表現」した世界が広がっています。 立体曼荼羅は「羯磨曼荼羅(かつま・まんだら)」とも呼ばれます。 講堂の曼荼羅を構成する仏像の多くは乾漆を併用した木彫像。 空海(弘法大師)の指導のもと、仁王経曼荼羅を二十一体の仏像を配置することで表現しています。 その内訳は、五仏(五智如来)と五菩薩・五明王・四天王に帝釈天と梵天を加えたものとなっています。 空海没後4年を経た承和六年(839)6月15日に完成、開眼されました。 火災消失・地震倒壊などにより、中央の五仏(重要文化財)及び、 菩薩の中心である金剛波羅蜜多菩薩の計六体は後補されましたが、 他十五体は全て平安前期を代表する国宝です。 平面に描かれた金剛界曼荼羅で、右を北として東西南北に描かれる諸仏は 講堂内では五智如来・五菩薩は実際の北西方向を北として、 五大明王・天部は実際の北東を北として配置されています。 |
|||||||||||||
|
|||||||||||||